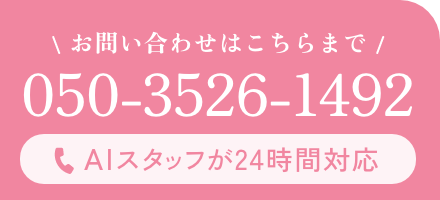院長コラム
顎(あご)の形は顔全体やフェイスラインの印象を大きく左右します。特に受け口の輪郭を持つ方は、顎が長い・しゃくれている・太く見えるといった悩みを抱えやすく、オトガイ形成やVライン形成を検討するケースが増えています。
しかし、手術法を誤ると「顎が太くなった」「輪郭が丸くなった」といった後悔につながることも少なくありません。
本記事では、形成外科専門医の経験をもとに、オトガイ形成とVライン形成の違い、そして受け口の輪郭で失敗しないための手術選びのポイントを詳しく解説します。
目次
オトガイ形成の基本とその目的
オトガイ形成とは、顎先(オトガイ)の骨を切って移動・切除することで形を整える手術です。顎先は顔のバランスを決定づける要素であり、ほんの数ミリの移動でも印象が大きく変わります。
主な方法は前方移動・後方移動・短縮・延長・左右移動で、それぞれに適応があります。たとえば後退顎なら前方移動、しゃくれなら後方移動といった具合です。
メリットとしてはEラインを整えやすく、侵襲も比較的少ない点が挙げられます。一方で、骨を短縮しすぎると皮膚が余り「顎が太く見える」こともあり、神経損傷や左右差のリスクも考慮が必要です。
Vライン形成の特徴
Vライン形成は、下顎角(エラ)から顎先までを削り、顔全体を細く整える手術です。顎先だけを調整するオトガイ形成と違い、下顎体を含めて広範囲に骨を整えるため、小顔効果が高いのが特徴です。
フェイスラインをなめらかにし、全体をV字型に導けるため韓国美容でも人気があります。ただし範囲が広いためダウンタイムは長く、神経への影響や平坦化のリスクもあります。
顎先とエラを同時に調整できる一方で、術後の腫れやむくみは強く、数週間は日常生活に制限が出ることも少なくありません。術後の仕上がりは魅力的ですが、適応を誤ると「思ったより自然さが失われた」という結果にもなり得るのです。
受け口の輪郭に潜むリスク
受け口(下顎前突)は、単に顎が大きいのではなく、上顎が後退して下顎が前に出ている骨格的特徴が関係しています。見た目だけを整えようとオトガイ形成を行うと、顎を短縮しても皮膚が余って輪郭が丸く見える、前に出すとしゃくれ感が強調されるなどのリスクがあります。
Vライン形成も同様で、骨を削っても皮膚の余りが解消されず、たるみや平坦化が強調されることもあります。特に受け口の方は「顎先だけ」で改善を図るのが難しく、骨格全体の評価が欠かせません。
カウンセリングではCT撮影を行い、骨格と咬合の両面から適切な術式を見極めることが重要です。
両顎手術が必要なケース
根本的な改善を望む場合、両顎手術(上顎+下顎骨切り術)が必要となることもあります。受け口は下顎の突出と上顎の後退が組み合わさっているため、オトガイ形成やVライン形成だけでは不十分な場合が多いのです。
両顎手術では、咬合の改善と輪郭の調整を同時に行えるため、横顔・正面ともにバランスの取れた仕上がりを得られます。
ただし侵襲が大きく、入院や長期のダウンタイムを伴うのが難点です。
それでも、噛み合わせの改善は長期的な健康にも直結するため、美容目的にとどまらず医療的な意義もあります。
軽度であればオトガイ形成で対応可能ですが、中等度以上の受け口では両顎手術が選択肢に上がることを知っておくべきです。
オトガイ形成で顎が太くなる?
実際に「オトガイ形成をしたら顎が太くなった」と修正のご相談に来院される方が増えています。
たとえば顎先を短縮しすぎて皮膚が余り、結果的に幅広い印象になったケース。
後方移動を行った結果、しゃくれが強調されたケース。
あるいはVライン形成で過剰に削り、顔全体が平坦化して立体感を失ったケース。
いずれも共通するのは、骨格全体の評価が不十分だったことです。患者の希望をそのまま反映させただけでは、必ずしも理想的な結果につながりません。
専門医は咬合や皮膚の状態まで含めて診断し、必要に応じて脂肪吸引や糸リフト、矯正治療との併用を提案します。こうした対応が、術後の満足度を大きく左右すると考えています。
骨切り術後・生活上の注意点
輪郭手術は結果だけでなく、術後の経過管理も非常に重要です。
術後1週間は腫れと内出血がピークで、会話や食事に制限がかかります。2〜3週間経過すると腫れは落ち着きますが、食事はまだ柔らかいものが中心です。
1か月で社会復帰できる方が多いものの、感覚の違和感やしびれは数か月残ることもあります。完成形に近づくのは3〜6か月で、ここまでを「経過観察期間」と捉える必要があります。
また、術後は飲酒・喫煙・激しい運動を控えることが推奨され、冷却や歯磨きなどのセルフケアも重要です。こうした過程を理解して臨むことで、精神的にも安心してダウンタイムを乗り越えることができます。
咬合と矯正治療の重要性
輪郭手術は「見た目」だけの問題ではなく、「噛み合わせ(咬合)」とも密接に関わります。特に受け口の場合、歯列矯正や咬合治療を併用しなければ根本的な改善は難しいことが多いです。
例えば下顎だけを削っても上顎の後退がそのままではバランスが崩れ、横顔が平坦に見えることもあります。
また、噛み合わせが改善しないまま骨を操作すると、顎関節に負担がかかり長期的なトラブルにつながることもあります。
輪郭手術を検討する際は、美容外科と矯正歯科、形成外科が連携し、多角的に治療プランを立てることが理想です。外見と機能の両面を意識したアプローチこそが、後悔のない結果につながります。
まとめ:受け口で失敗しないために
-
オトガイ形成は顎先限定 → 小回りが利くが限界あり
-
Vライン形成は下顎全体 → 効果は大きいがリスクも伴う
-
受け口は両顎手術が必要になることが多い
-
皮膚・脂肪・咬合の評価を怠ると失敗リスクが高まる
-
CT解析と専門医によるカウンセリングが不可欠
よくある質問(FAQ)
Q1. オトガイ形成だけで受け口は治せますか?
A. 軽度の症例では改善することもありますが、骨格性の受け口はオトガイ形成だけでは根本的に治りません。多くの場合、両顎手術や矯正治療が必要となります。顎先だけを動かす手術と骨格全体を調整する手術の違いを理解して選択することが大切です。
Q2. 顎を短縮すると必ず太くなりますか?
A. 必ずではありませんが、骨を短くすることで皮膚が余りやすくなり、横幅が広がって太く見えるリスクはあります。皮膚のたるみを抑えるために脂肪吸引や糸リフトを併用することもあり、術後の経過に応じて追加治療を検討するのが一般的です。
Q3. Vライン形成のダウンタイムはどれくらいですか?
A. 腫れやむくみは術後2〜4週間ほど続きますが、日常生活に支障がなくなるのは1か月前後が目安です。最終的な完成は3〜6か月後で、知覚の違和感や感覚の鈍さがしばらく残ることもあります。手術範囲が広い分、回復には時間がかかると理解しておきましょう。
Q4. 両顎手術を受けるとどのくらい休養が必要ですか?
A. 社会復帰には仕事内容にもよりますが、1〜4週間が目安です。体力の回復や咬合の安定には数か月を要することもあります。美容目的だけでなく、咬合や健康面の改善にも関わるため、長期的な計画を立てて臨むことが重要です。

詳しくはユーチューブでご視聴ください。
監修者情報

宮﨑 邦夫
リノクリニック東銀座 院長【資格・所属学会】
日本外科学会専門医 / 日本外科学会会員 / 日本形成外科学会会員 / 日本頭蓋顎顔面外科学会会員 / 日本美容外科学会会員
消化器外科・心臓血管外科・呼吸器外科・小児外科など外科研修ののち、外科専門医を取得。その後、形成外科で6年、美容外科で7年実績を積み、リノクリニック東銀座を開業、院長を務める。美容外科の技術は韓国や台湾、アメリカなどへ出向き、良質な技術を取り入れて日々の診療に生かしている。 2014年から在籍していた湘南美容クリニックでは指導医として若手美容外科医の教育にも尽力し、同院で行われた美容外科コンテストで2年連続ではグランプリを獲得。次の東京美容外科では骨切りメニューの立ち上げを行い、スタッフ教育にも尽力した。
監修日:2025.09.25