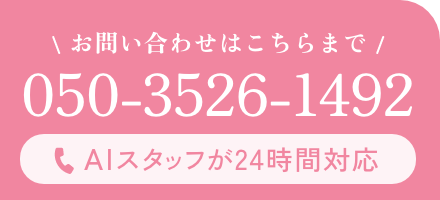院長コラム
エラ切り・エラ削り(下顎角整形)の基本知識―術式やダウンタイムまで解説
下顎角(エラ)の整形は、エラ削りやエラ骨切りと呼ばれフェイスラインを整えたいと考えている多くの方に注目されている骨切り治療です。骨格のバランスによって顔の印象が大きく左右されるため、下顎角の突出やホームベース型の輪郭を改善する術式として広く行われています。
手術では、下顎骨と周辺組織の構造的特徴を理解し、CTや3Dシミュレーションを用いた詳細な分析と安全対策を行います。また術式には骨を切除する方法や筋肉・脂肪組織を除去する方法があり、個人の希望や顔の形状によって最適なアプローチが選択されます。
本記事では、下顎角(エラ)の解剖学的特徴や手術方法、術前・術後の流れ、リスクなどを総合的に解説します。初めて下顎角形成術を検討する方でもわかりやすいよう、基本的なポイントを押さえながら紹介していきます。
目次
下顎角(エラ)とは
下顎角とは、下顎体と下顎枝が交わる隅角部のことを指します。顎を動かす際に重要な役割を担う部分であり、咀嚼運動や顔のシルエットに影響を及ぼすため、美容整形を行ううえでも注目されます。年齢や咬み合わせの状態によって骨組織や筋肉の発達具合が変化し、下顎角の突出度合いに差が生じます。
無歯顎の状態が長期化すると、下顎角が広がりやすいといわれますが、一般的には日常の咀嚼頻度や筋肉の発達によってエラの形が大きく左右されます。エラを控えめに見せるためには骨だけでなく、筋肉や脂肪など軟部組織の影響も考慮する必要があります。
口腔内の神経走行や血管支配を把握することは、下顎角形成術の安全性を高めるための最重要事項といえます。特に下歯槽神経や顔面神経の位置には細心の注意を払い、術後の感覚障害や表情動作の障害を防ぐよう配置や切除範囲を吟味して施術を進めます。
下顎角形成術(エラ削り・エラ切り)と下顎骨の役割
下顎骨は頭部唯一の可動性を持つ骨格であり、咀嚼や発声に深く関わります。その基部である下顎角は、フェイスラインを左右する重要な部位で、角度や厚みのわずかな違いが顔全体の印象を変えます。骨格の形状が顕著に目立つ場合は、骨切りによるアプローチが検討されることがあります。
下顎角と咬筋が輪郭に与える影響
エラ部分には咬筋という強力な筋肉が存在し、食事や会話など日常的な活動で頻繁に使われます。この筋肉が発達しすぎると、下顎角そのものが強調され、エラが張って見えやすくなります。骨切り手術だけでなく、筋肉の減量術を組み合わせることで、より自然なフェイスラインを得られるケースもあります。
下顎角形成術と下歯槽神経リスク
下歯槽神経は下顎骨の内部を走行し、下顎の歯列や下唇、顎先部分の感覚を司る大切な神経です。手術時には神経の保護が極めて重要で、骨切りの深度や位置を誤ると、長期的な感覚障害やしびれを引き起こす可能性があります。CT画像による精密な術前診断が、神経リスクを最小化するカギとなります。
下顎角形成術と頬脂肪体の関係
頬脂肪体は、頬の内部にある塊状の脂肪組織で、顔のふくらみや輪郭を形成する重要な要素です。下顎角形成術において、骨だけを削るだけでは理想的なフェイスラインに達しない場合、頬脂肪体切除を併用するケースも検討されます。顔のバランスを考えた包括的なプランニングが、満足度の高い仕上がりを導きます。
下顎角形成術(エラ削り・エラ切り)の種類
次に、実際に行われる下顎角形成術の代表的な手術方法について解説します。
下顎角形成術には、骨を広範囲に切除する方法から外側の骨板を削る程度の軽度な方法までさまざまな術式があります。患者の骨格・筋肉の状態や希望する輪郭によって最適な方法が選択され、過度な削りすぎは不自然なラインを生むため注意が必要です。
近年では口腔内からのアプローチを採用することで、外部に傷跡を残さずに手術を行えるケースが増えています。3D模型やCT画像に基づいたシミュレーション技術の発展もあり、一人ひとり異なる骨格に合わせて安全かつ正確に施術できる点が大きな特徴です。
また、骨切り単体で十分な効果が得られない場合は、筋肉や脂肪組織の処置を併用することが検討されます。例えば咬筋を薄くする咬筋減量術や、頬脂肪体切除などを組み合わせることで、よりシャープで立体的なフェイスラインを目指せます。
拡大下顎角骨切り術の特徴と注意
下顎角を大きく切除し、フェイスラインを劇的に変化させる方法です。頬からエラまでの骨格全体を広範囲に調整できる一方、切除範囲が広がるため傷口や神経保護には特に細心の注意が必要となります。骨の切除量を適切にコントロールすることで、より自然なシルエットを形成できます。
外板切除|下顎角形成術の方法
外板切除は、下顎角の外側にある骨の外板を削ることで、エラの横張りを改善する手術です。切除量を調整しやすく、エラがやや張っている程度であれば大幅な変化を必要とせず、比較的軽度なダウンタイムで済むメリットがあります。過度に削りすぎると不自然になるので、慎重なデザインが肝心です。
下顎角形成術と咬筋減量・脂肪除去
骨の切除だけでは効果が十分でない場合、咬筋減量術や頬脂肪体切除を併用します。咬筋をRF(高周波)などで部分的に減量することで筋肉のボリュームを落とし、輪郭をすっきりとさせることが可能です。頬脂肪体切除は笑った際に大きく膨らむ頬のボリュームを抑える効果があり、患者の個別のニーズに合わせて検討されます。
非外科的治療のエラボトックス注射
咬筋の発達によってエラが強調されている場合には、エラボトックス注射(ボツリヌストキシン注射)も選択肢の一つです。筋肉の働きを一時的に抑えることで、数週間から数ヶ月かけて咬筋が縮小し、フェイスラインがすっきり見える効果が期待できます。
外科的な骨切りに比べてダウンタイムが短く、日常生活への影響が少ないため、まずは非外科的な方法を試したい方にも適しています。ただし効果は永久ではなく、4〜6か月ごとに繰り返し注射が必要な点は理解しておきましょう。
下顎角形成術の術前評価とデザイン
下顎角形成術では正確な骨格評価とシミュレーションが重要となります。術前デザインのポイントを見ていきましょう。
骨格構造は個人差が大きく、例えばホームベース型やU字型など、あご先を含む輪郭全体の形によってデザインの組み立て方が異なります。術前にはCTスキャンやレントゲンを用いて正確な骨量や神経位置を把握し、減量できる範囲や切除角度を慎重に検討します。
適切な評価を行わずに手術を進めると、十分な効果が得られないばかりか、神経損傷のリスクが伴う場合もあります。3Dシミュレーションでは、骨切り後のフェイスラインを視覚的に確認できるため、カウンセリングでのイメージ共有がしやすくなります。
下顎角形成術の横顔・正面骨格分析
横顔や正面からの分析は、下顎角の張り具合だけでなく、顎先や頬骨とのバランスを総合的に把握するために欠かせません。CTやX線など画像技術を活用して、下顎骨全体の厚みや角度をミリ単位で測定します。その結果を元に理想のフェイスラインに近づけるため、切除範囲や角度を精密に設定していきます。
下顎角形成術の3Dモデルシミュレーション
個々の骨格を反映させた3Dモデルを使えば、患者が術後の仕上がりを事前にイメージしやすくなります。特に、神経や血管の位置を可視化できるため、安全な切除ラインの計画が可能になります。こうした精密シミュレーションは、患者と医師のコミュニケーションを円滑化し、より安心感を持って手術に臨めるメリットがあります。
下顎角形成術の流れと基本手順
手術当日の流れや基本的な手術の進行段階を把握することで、不安を軽減し安心して臨むことができます。
下顎角形成術は通常、全身麻酔で行われることが多く、入院または日帰り手術の形態を選択できます。術前準備として患者の口腔内を清潔に保ち、マーキングを行い、正確な切開位置を決定します。手術によっては、唇や頬の中を切開するため、神経や血管に配慮した手技が求められます。
切開から骨切りまでの流れは比較的シンプルですが、神経保護と出血管理は非常に重要です。特に下歯槽神経の位置を避けながら骨膜下を丁寧に剥離し、事前計画通りに骨を切除・削る必要があります。適切なドリルや工具を使い、患者の顎の形に合わせて微調整を重ねながら進める工程です。
最後に骨切り後の切開部を縫合し、感染を防ぐための処置を施します。術後は腫脹や疼痛がある場合もありますが、適切な痛み止めや止血処置によって次第に落ち着いていきます。術後経過をしっかり観察することで、合併症の発生を抑えながら安定した回復を目指します。
下顎角形成術の麻酔と切開の注意点
通常は全身麻酔を行い、手術中の痛みや不快感を最小限に抑えます。口腔内への切開は外部の傷跡を回避できるメリットがある一方、視野が制限されるため熟練した技術が不可欠です。骨膜を剥離する際は、神経と血管を損傷しないようにすることが何より重要です。
下顎角形成術の骨切りと補助的処置
事前に計画した切除ラインに沿って骨を切り、不要な部分を除去します。エラのラインを整えた後、咬筋や脂肪の処置を同時に行うことが多く、面倒をかける要因を一度の手術で解消しやすい点が利点です。手術では出血を抑制するために血管収縮剤や丁寧な止血措置を併用しながら慎重に進められます。
下顎角形成術の縫合と術後管理
骨切りが終わったら、切開部を縫合して最終的な止血を行います。口腔内の傷は外からは見えませんが、感染リスクや唾液による刺激を防ぐため、術後の口腔ケアがとても大切です。医師の指示に従い、うがい薬の使用や柔らかい食事への切り替え、適切な抗生物質の服用を行うことで早期の回復を促せます。
術後経過とダウンタイム
下顎角形成術後のダウンタイムや、よく起こり得る症状への対処法について把握しておくことは重要です。
術後は一時的な腫れや痛みが生じるほか、口を大きく開けにくい状態が続くことがあります。通常、2〜4週間程度で腫れが落ち着き、徐々に本来の輪郭が現れてきます。個人差はありますが、完全な定着には半年ほどの期間が必要とされるケースも少なくありません。
耳下腺や顎下腺周辺の腫脹がみられる場合、アイシングや適切な圧迫療法が有効です。痛みが続く場合には医師の処方する鎮痛剤を使用し、症状が長引くようであれば早めに受診し経過を確認してもらいましょう。
また、頬や唇に知覚の鈍さがみられる場合がありますが、多くは時間経過とともに回復傾向を示します。術前に神経位置を正確に把握し、手術中に損傷を最小限に抑えることで、症状が長引かず済むことが期待されます。
腫脹や知覚鈍麻などの症状と対処
手術直後から1週間程度は腫脹が目立ちやすく、顎周りの知覚低下が生じることがあります。冷却や圧迫などの適度なケアを行うとともに、血行を促進する軽いマッサージを行うと回復が早まります。ただし、完全な感覚戻りには数週間が必要であり、焦らず経過観察を続けることが重要です。
開口制限とリハビリのポイント
一時的に開口が制限されるのは下顎角形成術の特性上、避けられない可能性があります。手術後の数日間は柔らかい食事を心がけ、医師の指導のもとで徐々に口を開けるリハビリを進めましょう。無理に顎を動かすと内出血や痛みが増す場合があるため、段階的にトレーニングを行うことが大切です。
考えられるリスク・合併症と対処方法
外科手術であるため、術後に想定されるリスクや合併症への理解が必要です。
どのような外科手術にも合併症はつきもので、下顎角形成術もその例外ではありません。特に神経損傷、感染、出血などは重篤化すると後遺症に発展するおそれがあるため、医療機関の選択や執刀医の経験が重要です。術後のフォローアップ検診で早期発見・早期対処すれば、多くのトラブルは回避できます。
骨切り範囲が広い手術では血行障害が起きやすく、患部への栄養補給や免疫力が一時的に落ちる場合があります。医師の指示どおりに定期的な診察や適切な服薬を行い、腫れや違和感が長引くときは早めに相談することで深刻な問題へと進むのを防げます。
神経損傷や感染の可能性
下顎角形成術で最も注意が必要とされるのは、下歯槽神経などの損傷です。麻痺やしびれ感が長期化すると生活への影響も大きくなるので、術中の神経保護が不可欠となります。また、術後の腫脹や出血を放置すると感染症のリスクも増すため、処方された抗生物質やアフターケアの徹底が重要です。
血行障害や顎下腺のレリーフ化など
骨を広範囲に切除する場合、局所の血流が一時的に低下することがあり、術後の回復を遅らせる要因になります。また、骨や軟部組織の位置関係が変わることで、顎下腺や他の腺組織が明確に浮き出て見える『レリーフ化』が起こる可能性もあります。こうした症状を適切に理解し、術後の管理を慎重に行うことが成功のカギです。
下顎角形成術と併用される追加施術
骨格の形状や組織の特性によっては、希望どおりの結果を得るために追加の施術が必要となる場合があります。
下顎角形成術だけで理想のフェイスラインを完全に実現できるとは限りません。骨格要因に加え、咬筋の肥大や脂肪の量、皮膚のたるみなど複合的な要素が絡むからです。希望に沿った最終的な輪郭を得るために、咬筋ボトックス注射やフェイスリフトなどの追加施術が検討されることもあります。
下顎骨整形の症例

エラ削り(下顎骨整形)の症例 斜め45度

エラ削り(下顎骨整形)の症例 横顔
術前は下顎角の張りによってフェイスラインが角ばって見え、顔全体に硬い印象がありました。下顎角形成術により骨格のボリュームをコントロールし、顎下からエラにかけてのラインを滑らかに整えています。
術後は横幅の張りが軽減され、輪郭がすっきりとシャープになりました。正面からの印象も自然に引き締まり、男性らしさを残しつつもよりバランスの取れた顔立ちに改善しています。
当院には、国内はもちろん海外や遠方からのご相談も多く寄せられています。特に韓国で骨切り手術を受けた方が、感染や左右差、輪郭の不自然さなどの修正を目的に来院されるケースも少なくありません。骨切り手術は専門性の高い領域であり、初回はもちろん、修正においても安全性と確実性が重視されます。
この症例のように、患者様一人ひとりの骨格や筋肉の状態を分析し、適切な術式を組み合わせることで、自然でバランスの取れた仕上がりを目指すことが可能です。
よくある質問(Q&A)
Q: 術後はいつから仕事に復帰できますか?
A: ダウンタイムは個人差がありますが、デスクワークなら術後1週間程度で可能になることが多いです。個人差があるため、腫れが落ち着く時期を考慮して、無理のないスケジュール調整を心がけましょう。詳しくはカウンセリングで医師に相談をしてください。
Q: 手術跡は目立ちますか?
A: 多くの場合、口腔内からの切開を行うため外部に傷跡は残りません。口の中の縫合跡は徐々に薄れ、数ヶ月も経てばほとんどわからなくなります。
まとめ
下顎角形成術はエラの張りを改善し、すっきりとしたフェイスラインを目指す有効な手段です。しかし、骨格や筋肉、神経など多岐にわたる要素を総合的に考慮しなければ、思わぬ合併症を招く可能性があります。CT解析や3Dシミュレーションなどの技術を活用し、執刀医と十分にカウンセリングを行うことが大切です。
術後は痛みや腫脹などのダウンタイムを経て、最終的な輪郭が定着するまでには数ヶ月を要します。アフターケアの徹底や定期検診の受診を怠らず、感染症などの合併症や後遺症を未然に防ぎましょう。適切な医師と十分な情報をもとに計画を立てれば、満足度の高い仕上がりを得ることができるでしょう。
監修者情報

宮﨑 邦夫
リノクリニック東銀座 院長【資格・所属学会】
日本外科学会専門医 / 日本外科学会会員 / 日本形成外科学会会員 / 日本頭蓋顎顔面外科学会会員 / 日本美容外科学会会員
消化器外科・心臓血管外科・呼吸器外科・小児外科など外科研修ののち、外科専門医を取得。その後、形成外科で6年、美容外科で7年実績を積み、リノクリニック東銀座を開業、院長を務める。美容外科の技術は韓国や台湾、アメリカなどへ出向き、良質な技術を取り入れて日々の診療に生かしている。 2014年から在籍していた湘南美容クリニックでは指導医として若手美容外科医の教育にも尽力し、同院で行われた美容外科コンテストで2年連続ではグランプリを獲得。次の東京美容外科では骨切りメニューの立ち上げを行い、スタッフ教育にも尽力した。
監修日:2025.09.09