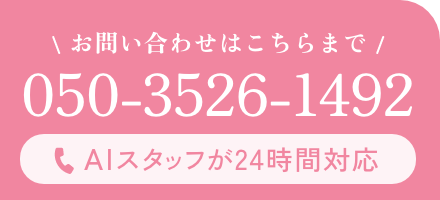院長コラム
目次
ルフォーⅠ型骨切り術とは?
ルフォーⅠ型骨切り術(Le Fort I)は、上顎骨を水平に骨切りし、上顎全体を三次元的に移動させる外科手術です。顎矯正手術(Orthognathic Surgery)の代表的な方法であり、主に上顎前突、開咬、ガミースマイル、中顔面の突出や後退といった症状に適応されます。
上顎を前後・上下に動かしたり、回転を加えて調整することで、噛み合わせの改善だけでなく、顔貌や口元の印象を大きく改善することが可能です。
ルフォーⅠ型手術で期待できる効果
-
噛み合わせ(咬合)の改善
-
ガミースマイルの改善
-
横顔のEラインの整備
-
中顔面バランスの向上
特に「インパクション」と呼ばれる上方移動は、笑った時の歯茎露出を減らし、下顎の自動回転によりフェイスラインが引き締まる効果もあります。機能改善と同時に審美性の向上を実現できる点が大きな魅力です。
ルフォーⅠ型骨切り術の適応とリスク
適応
ルフォーⅠ型骨切り術は、歯列矯正だけでは改善が難しい「骨格性の不調和」に適応されます。
-
上顎前突
-
開咬(奥歯だけが当たり、前歯がかみ合わない)
-
ガミースマイル
-
中顔面の過成長/後退
リスク
-
手術後の腫れやむくみ(ピークは術後1週間前後)
-
一時的な知覚鈍麻(上顎前歯や鼻周囲)
-
出血や感染のリスク
-
術後矯正が必要となるケース
ほとんどは数週間〜数か月で改善しますが、稀に知覚異常が長期的に残ることもあります。血管や神経が豊富な部位であるため、熟練した口腔外科医の技術が重要です。
SSRO(下顎枝矢状分割術)の特徴
SSRO(Sagittal Split Ramus Osteotomy:下顎枝矢状分割術)は、下顎骨を矢状面に沿って分割し、骨片を前後に移動させて固定する手術です。受け口(下顎前突)やしゃくれの改善に多く用いられます。
SSROのメリット
-
骨片同士の接触面が広いため、術後の安定性が高い
-
骨癒合が比較的安定しやすい
-
顎間固定の期間を短縮できる場合もある
SSROのリスク
-
下歯槽神経の損傷による下唇や歯茎のしびれ
-
腫れやむくみ(術後数週間)
-
一部でしびれが長期的に残るケースもある
ルフォーⅠ型骨切り術とSSROの違い
両者は「上顎を動かすか、下顎を動かすか」で明確に分けられます。
| 手術法 | 主な対象 | 改善できる症状 | リスクの傾向 |
|---|---|---|---|
| ルフォーⅠ型 | 上顎 | ガミースマイル・上顎前突・中顔面の突出/後退 | 鼻・上顎周囲の腫れ、知覚麻痺 |
| SSRO | 下顎 | 下顎前突・受け口・しゃくれ | 下唇や歯茎のしびれ、神経損傷 |
単独で行うこともありますが、多くの症例では上下両方にズレがあり、両顎手術(OGS)として併用されます。
両顎手術(OGS)を同時に行う意味
両顎手術(OGS:Orthognathic Surgery)とは、ルフォーⅠ型骨切り術とSSROを同時に行い、上下顎を総合的に調整する手術です。
両顎手術で得られるメリット
-
咬合の大幅な改善(噛む・話す機能向上)
-
横顔のEラインの整備
-
顔全体のバランス改善(小顔効果・輪郭改善)
-
呼吸や発音の改善
単独の上顎手術・下顎手術では得にくい包括的な改善を、一度の手術で実現できるのが特徴です。
両顎手術後の食事が大切な理由
両顎手術(OGS)を受けたあとは、腫れや口の開けにくさによって、食事が大きな負担となります。特に術後1〜2か月は噛みにくさや飲み込みにくさから「思うように食べられない」というストレスを感じやすい時期です。
しかし、この期間の食事は回復スピードや腫れの引き方に直結します。栄養不足のまま過ごすと、体力が落ちるだけでなく、腫れや痛みの改善が遅れることもあるため、正しい食事管理がとても重要です。
術後〜2週間
-
腫れと痛みが強く、口を大きく開けるのが困難
-
流動食やペースト状のやわらかいものが中心
-
栄養ドリンクやプロテインを補助的に活用すると安心
術後2週間〜1か月
-
細かく刻んだやわらかい固形食を開始
-
食材を少しずつ大きめにしていくことで「口を開けるリハビリ」になる
-
ミキサー食だけに頼らず、あえて噛む動作を取り入れることが重要
術後1か月以降
-
口の開きが指2本〜3本入る程度になれば、矯正治療の準備が進む
-
柔らかいものから徐々に普通食に近づけていく
-
この時期から「栄養のバランス」と「口を動かすリハビリ」を両立させることが回復を早めるカギ
避けるべき食べ物とおすすめの食事
避けるべき食べ物
-
硬い食材(ナッツ、硬い肉、せんべいなど)
-
弾力が強く噛み切りにくい食材(イカ、餅など)
-
辛すぎる・熱すぎる刺激物
これらは口の開閉がまだ不十分な時期に無理をすると、傷口を引っ張って痛みを悪化させる原因になります。
おすすめの食べ物
-
柔らかい煮込み料理(おかゆ、雑炊、シチュー)
-
刻んだ野菜入りスープ
-
白身魚や豆腐などのタンパク質
-
プロテインや栄養ドリンク
ポイントは「柔らかくて栄養豊富」「噛む練習になるサイズ感」を意識することです。
栄養摂取と回復スピードの関係
術後4日目以降からは、体内で腫れを引かせる回復プロセスが始まります。このときにしっかり栄養を摂れていると、血管への水分戻りがスムーズになり、腫れの改善が早まる傾向があります。
逆に食事が十分に取れていないと、体力が落ちて活動量も減少し、腫れが長引く原因になることがあります。特に術後1週間の食生活は回復に大きく影響するため、できる限り栄養バランスを意識しましょう。
両顎手術で得られる見た目と機能改善
両顎手術は医療的には咬合改善が目的ですが、結果的に美容的な変化も大きく得られます。
-
横顔のEライン改善
-
小顔効果
-
中顔面のバランス改善
-
ガミースマイルの改善
骨格レベルでの修正により、矯正治療単独では得られない審美的効果が期待できます。
両顎手術の費用と保険適用
両顎手術は、顎変形症と診断され機能障害がある場合、大学病院や一部の医療機関では保険が適用されます。この場合、自己負担3割で20〜40万円程度で受けられるケースもあります。
一方、美容目的で行う場合は自由診療となり、200〜400万円程度が目安です。
当院では保険診療は行っておらず、美容目的の自由診療としてご案内しております。費用の詳細はカウンセリングにて個別にご説明いたします。
両顎手術と輪郭形成術の違い
両顎手術と輪郭形成術は似ているようで、目的と適応が異なります。
両顎手術(OGS)
-
噛み合わせ・骨格の改善が目的
-
矯正治療と併用されることが多い
-
入院が必要
-
保険適用されるケースもある
輪郭形成術
-
フェイスライン改善が目的
-
顎先・頬骨・エラなどを削る/切る
-
歯列や噛み合わせには影響しない
-
美容目的で自由診療
※両者の違いを一言で表すと「噛み合わせに関わるかどうか」です。
専門医選びとカウンセリングの重要性
両顎手術は高度な技術を要するため、経験豊富な顎顔面外科医・矯正歯科医のチームによる治療が不可欠です。
-
手術件数や実績
-
3Dシミュレーションの導入
-
術後フォロー体制
これらを確認し、納得できるまでカウンセリングを受けることが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q: 術後の腫れはどのくらい続きますか?
A: 強い腫れは1〜2週間で落ち着きます。完全に自然になるには数か月かかる場合もあります。
Q: 普通の食事に戻れるのはいつですか?
A: 術後1か月程度で軟食に移行し、2〜3か月で通常食に戻れることが多いです。
Q: しびれはどのくらい残りますか?
A: 数週間〜数か月で改善するケースが大半ですが、神経損傷の程度によっては長く残る場合もあります。
Q: 保険は必ず適用されますか?
A: 顎変形症と診断され、機能障害がある場合は保険適用されます。ただし、美容目的では自由診療となります。
監修者情報

宮﨑 邦夫
リノクリニック東銀座 院長【資格・所属学会】
日本外科学会専門医 / 日本外科学会会員 / 日本形成外科学会会員 / 日本頭蓋顎顔面外科学会会員 / 日本美容外科学会会員
消化器外科・心臓血管外科・呼吸器外科・小児外科など外科研修ののち、外科専門医を取得。その後、形成外科で6年、美容外科で7年実績を積み、リノクリニック東銀座を開業、院長を務める。美容外科の技術は韓国や台湾、アメリカなどへ出向き、良質な技術を取り入れて日々の診療に生かしている。 2014年から在籍していた湘南美容クリニックでは指導医として若手美容外科医の教育にも尽力し、同院で行われた美容外科コンテストで2年連続ではグランプリを獲得。次の東京美容外科では骨切りメニューの立ち上げを行い、スタッフ教育にも尽力した。
監修日:2025.08.31